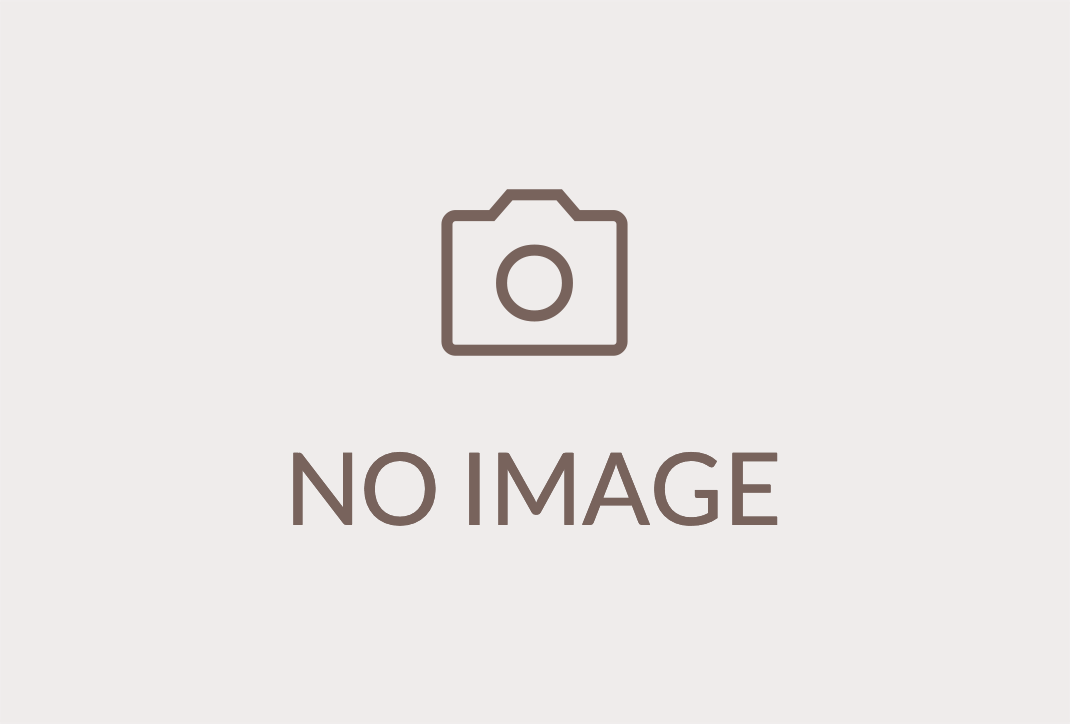捻挫の治し方は?足首や手首の捻挫の応急処置・マッサージ
2025.04.23
捻挫になる主な原因とは?

捻挫とは、関節まわりの組織損傷の総称で原因は様々です。
・階段を踏み外して足を挫いた
・スポーツ中に転倒して地面に肩を打ちつけてひねった
・中腰で荷物を持ち上げようとして腰をひねった
など、関節に急激な外力が加わり、関節可動域を超える動きを強いられて受傷に至るケースが多くを占めます。
それ以外では、長い時間歩いて足首の関節に荷重・捻転・負荷が加わって腫れた。
グリップを握るような動作を繰り返して指の関節に負荷を溜め込んで痛めるような、反復動作にともなうストレスにより関節周囲がダメージを受けて引き起こされるパターンもあり、これらはいずれもご自身が持つ関節の強度を超える負荷を受けたために発生しています。
捻挫と靭帯損傷は同じ?
違いはある?

どちらも関節周囲の組織損傷を指しますが、捻挫というケガの1つに靭帯損傷があると思ってください。
関節は骨とは別に筋、筋膜、腱、靭帯、関節包といった軟部組織で構成されています。
そのいずれが損傷しても捻挫と呼ばれることから、必ずしも単独で靭帯損傷とは言えないのです。
では、靭帯損傷とはどんな状態なのか?
関節組織の中でも、靭帯は関節を安定させる結束バンドのような役割を持ちます。
そのため靭帯が損傷すると腫れや痛みによる可動制限はもちろん、関節同士を結ぶ役割が失われると関節動揺性が発生します。
これを修復するには安静や圧迫・固定を中心とした保存療法を行いますが、ひどい場合は手術の適応となります。
捻挫の基本的な改善方法、
早く改善するための考え方

「捻挫」とは、関節のケガです。
具体的には、関節周囲の軟部組織の損傷を指します。
関節に大きな負荷が加わって受傷した場合、急性外傷の特徴的な初期症状である炎症が発生し、多くの患部で、「痛み」「熱感」「腫れ」「動きの制限」が生じます。
捻挫の施術では、こうした炎症を早い段階で抑える対処が早期回復のために重要となります。
炎症は受傷直後から1週間ほど続き、その間に患部周辺の組織を破壊し続けます。
そうした進行をできるだけ抑えるためには、患部のアイシングや固定はもちろん、急な外力によってズレた関節の位置関係を正常に整えたり、関節周辺の筋肉や筋膜、関節包の緊張を手技などで緩和する必要があります。
捻挫の部位ごとの応急処置
(足首、手首など)

受傷後すぐに当院で施術を受けていただけることが理想ですが、医療機関を受けるまでの間、症状を悪化させないためには、ご自身で応急処置を行う必要があります。
具体的には、「冷却」「安静」「挙上」です。
はじめに痛めた部分を氷や保冷剤などで10分程度冷やします。
これを1~2時間おきに最低3日間続けます。
湿布は初期症状に対してはほとんど効果がありません。
痛めた時と同じ動作をすると症状を悪化させますので、動かしたり体重をかけないで安静を保ってください。
就寝時は、枕やクッションで高さを調整し、患部を身体よりわずかに高く置いてください。
応急処置を実施したら、できるだけ早く医療機関に行き、適切な処置を受けてください。
捻挫に関するQ&A

Q. 捻挫どうしたら早く改善しますか?
A. 捻挫の応急処置は「安静・アイシング・圧迫・挙上」のいわゆるRICE処置が基本になりますが、一番重要なのはアイシングです。

Q. 捻挫を放っておくとどうなりますか?
A. 軽症、重症どの度合いでも靭帯が伸びて関節の固定力が低下するので、再度捻挫してしまう癖がついてしまいます。

Q. 捻挫したら病院に行くべきですか?
A. もし患部に痛みや腫れがあれば、すぐに整形外科などの医療機関や整骨院を受けることをおすすめします。

Q. 捻挫の痛みのピークはいつですか?
A. 捻挫は、靭帯や関節包・腱・毛細血管の損傷により疼痛や腫れ・内出血・浮腫みなどを伴い受傷後の炎症は24〜72時間後でピークを迎えます。

Q. 捻挫を自分で改善する方法はありますか?
A. 受傷直後は、冷湿布や氷で冷やして炎症を抑えて、その後サポーターやテーピングで軽めに固定し、心臓より高い位置に保ちましょう。
Q. 腰捻挫しやすい方の特徴はありますか?
A. ハイヒールなどを履いて足の甲とすね部分の角度が広がると緩みやすく、不安定になってひねりやすいです。
また、足首が硬い方(柔軟性がない方)は、捻挫しやすいと言われています。